
コロナの前から、旅の意義は少しずつ変化していましたが、アフター・コロナの時代に、旅の仕方も、好みも、変化はさらに加速していきそうです。2030年には「旅」というものはどうなっているのでしょうか?
さまざまなジャンルで活躍する人たちに「2030年の旅はどうなっているのか?」「その時に、大事な人に旅を贈るとしたら、どんな旅をつくる?」という話をwondertrunk & co.代表の岡本岳大がお伺いします。
違う世界を経験し世界観が変わるのは旅もVRも同じ
岡本
毎回さまざまなジャンルの方をゲストに迎え、今からだいたい10年先、2030年くらいの未来の旅について語ってきた本連載ですが、そのなかで、旅の体験がデジタル×リアルで進化していくというトピックがたびたび上がってきました。そこで9回目となる今回は、身体性メディアやハプティック(触覚)メディアがご専門の南澤先生に、身体の体験とデジタルテクノロジーの可能性について、旅という視点からお話を伺っていけたらと思っています。
この6月くらいから少しずつ海外の旅行者が戻りつつありますが、この2年間は本当に旅の価値、移動の意義について改めて考えさせられました。そんななか先生の研究領域を拝見すると、旅においてもものすごく大きな可能性を秘めているのではないかと感じます。
南澤
可能性があると同時に、もしかしたら脅威になるかもしれませんが(笑)。
岡本
そうですか(笑)。改めて、ご専門の内容について簡単にお伺いできますか。
南澤
もともと僕は2005年~2010年くらいにかけて、学生としてVRを研究していました。当時VRは知る人ぞ知る技術でしたが、ディズニーランドがある千葉県の浦安に住んでいたことからああいう体験づくりにとても興味を持っていて、VRも新しい体験を創造する技術として面白いなと思ったのが最初の研究のきっかけです。VRはメタバースにおいてひとつのインフラになるといわれていますが、僕らは1人1人の人間がそこで何を体験するか、そしてテクノロジーがいかに新しい経験を創り出し、その経験によっていかに人と人とのつながりが再構築されるかに関心があって、生身の身体だけでは得られない体験をどうテクノロジーの助けを得ながら実現させるかを研究しています。具体的には触覚を使って全身で体験できる装置だったり、アバターを使って離れた場所にテレポーテーションするような技術、あるいは尻尾をつけたり腕を増やすなど身体を拡張させるような技術を研究しています。そうした考え方のベースとなるのが、身体を僕らが世界とつながるための媒体ととらえる「身体性メディア」というコンセプトです。


岡本
なるほど。
南澤
僕らは身体感覚を通じて世界を認識しているので、旅などを通して自分がいつもと違う世界に行くことが新しい刺激になりますよね。実はその刺激は、いろいろな技術によってつくれるものでもある。メタバース、VR、XRも一つの旅だし、そうした経験を通して僕らの世界観はどんどん変わっていくものだと思うんです。また、たとえば人間は技術によって宇宙に行けるようになりましたが、飛行機にしろ自動車にしろ、ある意味人間の可能性の拡張ですよね。その考え方の延長線上で、人間そのもののポテンシャルを高める技術とは何か、ということを考えています。
岡本
そうなんですね。南澤先生は特にハプティク(触覚)技術の研究でも知られていますよね。
南澤
触覚は、学生時代から取り組んでいる仕事の一つです。VRは見る+聞くことで360度の世界が広がりますが、どうしても生身の身体は置いてきぼりになる。その点触覚は、自分の身体に対する気づきが得られるという点で非常に大事な感覚で、それを伝える技術を研究しています。たとえば僕らが開発したこの「TECHTILE toolkit(テクタイル・ツールキット)」という装置を使うと、紙コップの中にあるビー玉が転がる感じとか、炭酸飲料が注がれる触覚などを伝えることができます。
岡本
(装置に触れながら)本当ですね。すごい!


南澤
卓球の選手が持つラケットにこの装置を付ければ、スマッシュや回転の感覚を共有でき、プロの技術のすごさを体感できます。素材の質感も伝えられるので、たとえば織物製品など、オンラインショップで海外の人に買ってもらえるきっかけになるかもしれません。人間はいろんな感覚を統合して経験をつくっていますが、世界を見て感じて、頭の中でリアリティをつくっていますから、手にしているコップでこういう感覚がくると、経験から類推して「ビー玉が回っているな」とか「炭酸水が入ったな」と脳が判断する。情報としては単純で、触覚というものは意外と簡単に届けられるんです。いい意味でいかに人間が適当に生きているかがわかります(笑)。また過去にはプロバスケットボールリーグのイベントで、試合会場の床面と、ライブビューイング会場の床面にこの装置を設置しました。ドリブルやシュート後の着地など、床の振動を届けることで、遠隔地の観客がまるで間近で実際に試合観戦しているような臨場感を味わえたようです。
また、コロナ禍では欧米を中心に、ふれあいがなくなることによるストレス“スキンハンガー”が社会問題化しましたが、人が安心感を覚えたり信頼関係を築くのにふれあいは非常に重要。たとえばリモートワークやオンライン授業、遠方に住む家族とのコミュニケーションなどにおいても、一緒に何かを書くとか、つくるとか、食卓を共にするといったふれあいを再現することも可能です。食器の触れ合う振動とか、椅子を引く音などが伝わるだけで、結構そこにいる「気配」をつくることができるんです。オンライン診療であれば、患者さんが自分の脈を自分でとって、その感覚をそのまま医師に伝えられたりします。
ゲーム体験においては、ゲーム内のキャラクターがワープするときに全身に何かが突き抜けてくる感覚などを、全身スーツで届けることができます。体中の触覚が刺激されて、足裏で立っていることも忘れて空を飛んでいるような感覚になるなど、その世界に没入することができます。
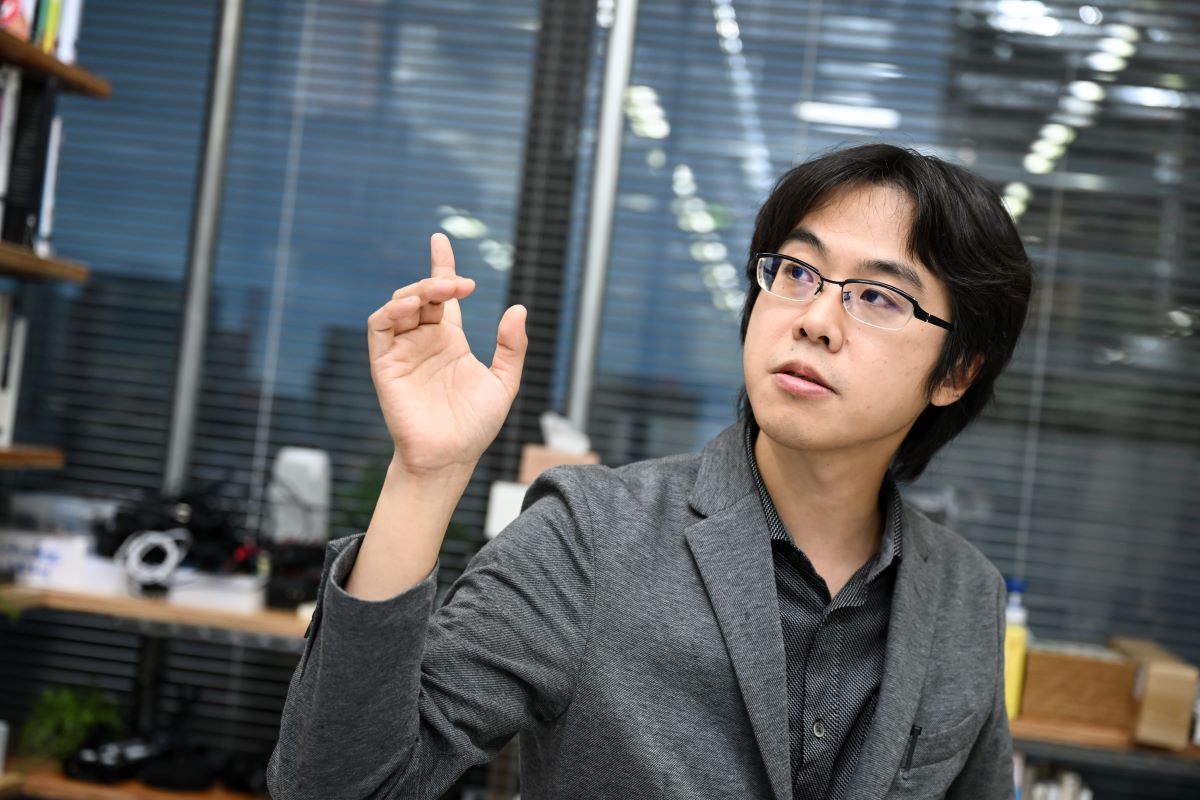
岡本
すごいですね。それからアバターやロボットの開発もされていますね。
南澤
はい。別世界にどう自分の身体をつくるかという研究もしています。たとえば遠隔地にいるロボットが見ているものを見て、聞いたものを聞き、触覚まで伝わってくると、自分が本当にロボットになりきって、その場にいるような感覚になります。こうした身体感覚を僕らはテレイグジスタンス(Telexistence)と呼んでいます。ロボットなら空を飛んだり小さくなったり、危険な場所にも行けるので、たとえば実際に雲仙普賢岳のような活火山の調査に活用しようといった実証実験も行われました。また、高齢のおばあちゃんが孫の結婚式にロボット越しに出席し、実際に新郎新婦と触れ合ってお祝いするような体験もできる。ロボットアバターは世界中のいろんな会社が取り組みを進めていて、宇宙ステーション内のロボットに入ることで、安全に宇宙遊泳を楽しめるような未来が、そう遠くないうちにやってくるはずです。
こうして遠隔に身体が拡張されると、たとえば日本の夜中に、ロボットを海外から遠隔操作し商品を棚に並べ、朝にはその作業が終えられていれば、日本の人が深夜労働をしなくても済むようになる。海外は海外で、遠隔操作する新しい仕事が生まれる。そうした瞬間移動を前提にすると、時差を有効活用できるし、働き方がもっと自由になるはずです。
もう一つ、制約を突破するという意味での可能性も最近注目されていて、寝たきりの方とロボットを通じて一緒に働くプロジェクトも進めています。オリィ研究所というスタートアップが運営されている、外出が困難な方たちが従業員として分身ロボットを遠隔操作し、接客する「分身ロボットカフェDAWN」では、普段家族や医療関係者としか接点がなかった方々が、ロボットをより自分らしく動ける体として操作し、多くの人とコミュニケーションをとっていて、生身の身体ではできなかったことが実現できています。大阪で一つのシフトが終わったら、次は群馬のシフトに入るなど、肉体に付随する制約から完全に自由な働き方の実践がはじまっています。
岡本
僕らもそのカフェにお邪魔して、場所の概念が覆されるようなユニークな感覚をおぼえました。VR、触覚の研究から始まって、可能性がどんどん広がっていく感じですね。
瞬間的な「体験」ではなく、時間積分がかかった「経験」を考える
岡本
改めて伺いたいのは、経験や体験の共有についてです。僕が旅の仕事を始めたのは10年ほど前で、ちょうど竹島や尖閣諸島問題があり、中国や韓国との関係がピリピリしていた頃でした。そうした国々のメディアやクリエイターたちと日本中を取材して回るなど、仕事を共にしていましたが、せっかくつくった日本を紹介するコンテンツを現地で流せなくなるなど制約も出てきていました。その際に彼らと話したのが、「国や政治の関係は変わるけど、自分たちが一緒に経験した価値は変わらないはずだから、それは時間をかけてでも伝えていこう」ということ。自分にとって原体験の一つで、その後ずっとこの仕事を続けたいと思ったモチベーションでもあります。同じ土地を踏み、同じ空気を吸って、一緒に体験してきた旅が、互いの誤解や偏見を解消してくれるのをすごく実感したんです。
先生のお話を聞いていて、テクノロジーによって身体経験や体験を共有することは、ある種旅と同様かそれ以上に、異文化交流や相互理解のチャンスにつながると思いました。冒頭で、先生の研究している技術が旅にとって脅威になるかもしれないといわれましたが、僕自身は旅にもいろんな形があると思うし、旅を通した相互理解、そして偏見をなくすことを目指している身としては、テクノロジーがその可能性をずっと広げてくれそうだと感じています。

南澤
おっしゃる通り、ちょっとした非日常を共体験する意味は大きいですよね。お祭りでも運動会でも、年に一度コミュニティの皆でイベントを共体験することによって、災害時に助け合いやすくなったり、卒業後の新たなつながりを生んでいたりする。いまはあまりにもコミュニティが大きくなりすぎてつながりにくくなり、共体験も生まれにくくなっていることが、さまざまな社会課題につながっているとも感じます。
そんななか、テクノロジーを使ってどんな体験共有ができるかということを僕らも試行錯誤しているところです。たとえばある装置を頭に装着することで認知症の方の世界を共有するという取り組みを行っていますが、これをかぶると、距離がわかりにくい、暗いところがよく見えない、明るいところはまぶしすぎる、視界が狭い…となり、自然と歩き方も手探りになって腰が曲がってくるんです。この体験を通して、医師や看護師の方も、患者さんの体験を追体験でき、より親身に向き合えるようになるなど、接し方や共感性が変わってきます。同様に、会社における上司と部下を入れ替えてみるとか、海外だと黒人と白人を入れ替えてみるとかの研究も行われていて、異なる立場のパースペクティブを体験することで人間関係における気づきを得られることにつながっています。さらに僕らは、二人羽織状態で、人と人を重ねることで一心同体にしてみるという取り組みも行っています。そうすると、2人で一つの身体を身にまとって仕事をしたり、作業をすることができる。あるいは2人の動きを完全にミックスさせることで、一人じゃできないことを少しずつ助け合って作業するということも行っています。
これまでは、身体は一つというのが大前提でしたが、それが変わってきているんです。自分の分身ロボットが2つ3つあってもいいし、あるいは一つの身体に2人いてもいいというわけです。

岡本
面白いですね。僕らの会社の旅行部門がターゲットにしている欧米の富裕層は、ある程度いろんな体験にお金をかけたいという人が多いんですが、たとえば伝統工芸の制作現場などに行くと、自分もやってみたいという人もいれば、プロに任せて完成品だけ購入したいという人に分かれる。ただ職人さんの身体に一緒に入れるとすれば、またまったく別の体験になりますよね。
南澤
熟練の職人さんと話すと、商品を買ってもらうこと以上に、その裏にあるプロセスとか技術を知ってほしいという声をよく聞きます。とはいえ皆に工房に来てもらうわけにはいかないので、いかに彼らの身体知・技を伝えられるかにも、僕らの研究の可能性があると思っています。触覚研究でよくご一緒している名古屋工業大学の田中由浩先生は、日本の吉野杉を使った工芸品を海外のセレクトショップに置くにあたり、お客さんにその製作工程を体感してもらえるような取り組みを行われていました。ヤスリをかける感覚や、木材を加工するプロセスなどを触覚を使ってオンラインで遠隔地に届けることで職人さんの技や身体感覚が埋め込まれたストーリーが生まれます。そうすることでプロダクトへの見方が変わるし、伝えられるストーリーも変わってきます。これまでエクスペリエンスというとどうしても瞬間的な感覚の話になっていましたが、いまはナラティブの重要性も問われるようになってきました。そこまで技術が成熟してきたことの現れだと思います。そうして経験を伝えられるようになれば、いままでとは違うレベルで情報を届けられるようになる。そこは僕もこれからもっとトライしていきたい領域です。ちなみに体験よりも時間的な積分がかかったものという意味で、意識的に「経験」という言葉を使うようになっています。
岡本
瞬間的な体験から、時間積分がかかった経験へ、ということですね。すごく納得します。
僕らの仕事でもまさにナラティブ、ストーリーテリングの発想を重視していますが、その際のひとつのポイントとなるのが、「旅マエ」「旅ナカ」「旅アト」という概念においてストーリーをどういう時間軸で伝えるかという点です。事前に伝えすぎてもネタバレになるし、かといって情報を出し渋りすぎては興味を持ってもらえないというジレンマがある。でもいまおっしゃったようなテクノロジーの使い方ができれば、一度遠隔で経験してみて、そのうえでリアルな旅につなげるということもできそうです。
南澤
味見みたいなものですよね。味見のときになるべく手軽に届けて、興味を持ってもらったうえで初めて、じゃあ行ってみようと思ってもらうのもいいかもしれませんね。選択肢が多すぎることで、何を選べばいいかわからず苦労するいまの世の中において、いくつもレビューを見て選ぶよりも、もう少し感覚的に情報を得て、本当に体験してみたいと思ったものを選ぶことができればいい。デジタルでできることはそれでいいけど、未知の経験をテクノロジーで知ってみて、それによって価値観も広がり、じゃあこの体験に生身を使おうという選択ができたら。生身の体験の価値はこれからますます高まるはずです。
岡本
本当にそうですね。
僕らの商品のひとつに、山形の出羽三山で山伏修行をする旅があります。こうしたスピリチュアルな体験に関心が高いお客さんの中には、あまり情報のない中現地でドキドキしたいという方も多くその想いにも応えたいのですが、実際には宿泊施設の様子とか服装とか、ある程度しっかりと情報提供してから来てもらった方の方が満足度が高い。自然のなかで山歩きをしたり滝に打たれたりすることで、五感が研ぎ澄まされる体験という最大の価値は、現地に来てからフルで味わってもらうとして、まずは映像を見せることも含めて、しっかり情報提供していこうと考えているところです。ですから、ある程度味見をしてもらうのは非常にありだなと思います。
南澤
たとえば教育現場の場合は、時間的制約、人的制約があり、味見しかできませんよね。全員がフルスペックの生の体験ができないときでも、いい味見をたくさんすることは、すごく大事だと思うんです。それによっておそらく人生の選択肢がすごく広がる気がします。なんなら鳥や魚になってみることも可能です。ある海外の研究では、イソギンチャクの時間で海を眺めた結果、海洋汚染の様子を目にすると非常に共感性が高まり、自然環境への意識が高まることが報告されています。あるいは、VRで高いところに行くと普通は足がすくむけど、「あなたは鳥です」という暗示をかけられた上だと、VRで意外と平気で飛べることもわかっています。つまり自分が何者かという感覚も変えられる。山伏体験の話も、それこそ自分が山伏になったように感じることで、五感が研ぎ澄まされるんでしょう。
ある程度デジタルで体験したうえで、「じゃあ自分は何者になろう」と決めて、実際の体験をすることができる。やりたくてもできないことを突破することで、バリアをなくしていけるのではないかと思います。
2025年の大阪・関西万博における日本政府館の基本構想にもかかわらせていただきましたが、その時の構想メンバーが皆共通して大事にしていたのは、1つにはこのような、個人という存在を超えて他人や地球環境そのものへの共感を感じられる体験を生み出すこと、もう1つには、誰もが自由に自分のやりたいように、万博にアクセスできる環境を整えることです。遠くにいる人も近くにいる人も、生身であれアバターであれ、いろんなかたちでアクセスできる環境にすることが、本来のダイバーシティでありインクルージョンだと考えています。
岡本
なるほど。「何者になるか」という大きなジャンルがあるのは面白いですね。
≪後編へつづく≫

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 (KMD) 教授
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業 Project Cybernetic beingプロジェクトマネージャー
専門分野:身体性メディア、ハプティクス(力触覚)、バーチャルリアリティ、身体情報学、システム情報学
2005 年東京大学工学部計数工学科卒業、2010 年同大学院情報理工学系研究科博士課程修了、博士(情報理工学)。メディアデザイン研究科特任助教、特任講師、准教授を経て2019 年より現職。
KMD Embodied Media Projectを主宰し、身体的経験を伝送・拡張・創造する「身体性メディア」の研究開発と社会実装、Haptic Design Projectを通じた触覚デザインの普及展開、新たなスポーツを創り出す超人スポーツやスポーツ共創の活動を推進。日本学術会議連携会員、超人スポーツ協会理事・事務局長、テレイグジスタンス株式会社技術顧問等を兼務。慶應義塾大学義塾賞、計測自動制御学会技術業績賞,日本バーチャルリアリティ学会論文賞・学術奨励賞、グッドデザイン賞など各賞受賞
KMD Embodied Media Project — https://www.embodiedmedia.org
JST Moonshot | Project Cybernetic being — https://cybernetic-being.org
Haptic Design Project — http://hapticdesign.org

株式会社wondertrunk&co. 代表取締役共同CEO
2005年博報堂入社。統合キャンペーンの企画・制作に従事。世界17カ国の市場で、観光庁・日本政府観光局(JNTO)のビジットジャパンキャンペーンを担当。沖縄観光映像「一人行」でTudou Film Festivalグランプリ受賞、ビジットジャパンキャンペーン韓国で大韓民国広告大賞受賞など。国際観光学会会員。








