
ペラペラほんだなとは
大利、德岡、松村3名による朝日広告賞への応募作品。講談社から出された課題「読書をテーマに子どもたちが喜び、興味を示すような新聞広告を!」を扱ったもの。「新聞読者が子どもや孫に思わず見せたくなる、子どもたちが本に興味が湧くような新聞広告を見せてください。」という課題に対し、新聞紙面を本棚に見立て、本の背表紙に添えられたQRコードから絵本の世界へ飛べるというアイデアを提案した。紙面に載せた本のタイトルは、すべて講談社から出版されている児童書。だれでも楽しめるよう極力シンプルな仕掛けで、世の中にたくさん存在する本と子どもが出会うきっかけを新聞広告の中で表現している。


紙面に載せた本のタイトルは、すべて講談社から出版されている児童書のタイトル。本の背表紙にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、端末上で絵本が読める仕組み。
こどもが本と出会う入り口になる「ペラペラほんだな」
―三人でチームを組んだきっかけについて教えてください。
大利:僕らは今年で入社4年目の同期で、もともとは入社後のクリエイティブ研修でよく話すようになりました。所属先はばらばらですが、僕と德岡は家が近所ということもあってよく飲んでいて。せっかくだから朝日広告賞に応募してみようかという話になり、德岡と仲の良かった松村も加わって、3人で挑戦しようということになりました。

德岡:まず取り掛かったのが「新聞広告の部」で、そちらには15作品を応募しました。その入稿がほぼ終わりつつあった締め切りの直前、3人でカツ丼を食べながら、「デジタル連携の部」にも追加で応募してみようかという話になったんです。
―新聞紙面を本棚に見立て、紙面のQRコードを読み取ると絵本が読めるというアイデアは、どのように生まれたのですか。
松村:「新聞広告の部」で別出版社の課題に取り組んでいたこともあり、すでに新聞広告と本についてはいろいろと思考を巡らせていて、アイデアの種が溜まっていた状態でした。なので「デジタル連携の部」も、講談社の課題にしようとすんなりと決まりました。紙面を本棚に見立てたのは、子どもには、本がいかに楽しいか理屈で伝えるんじゃなくて、実体として目の前に本棚がそこにあるくらいシンプルな方が心が動くと考えたから。子どもたちが本に対して興味を持って、実際に触れてもらうための、出会いの入り口をつくることができるんじゃないかと思います。
德岡:どんな仕組みでデジタル連携させるかについては少し悩みましたね。スマホ上で完結してしまえるようなものではなく、現物として存在する紙メディアらしさを活かし、新聞を実際に開いてみたくなるようにするには何が必要なのか、3人で意見を出し合いました。
大利:結果的に、ARなどではなく、QRコードを使ったとてもシンプルな仕組みになりました。受け手は最先端のデジタル技術に詳しい人ではなく、あくまでも子どもたちであり、我々のような一般の人ですから。小難しいものにしなかったのはかえって良かったですね。シンプルがゆえに、飽きることなく楽しんでもらえると思います。

フラットな視点から意見を出し合い、わかりやすさ、伝わりやすさを追求
―それぞれどのような役割分担で、どんなことを意識して臨みましたか。
松村:大利はデザイナーで、僕と徳岡はコピーライターですが、あんまりその役割に囚われることなく自由にアイデアを出し合いました。ビジュアルだけで成立する、コピーのないアイデアもすごく好きですし、思いついたことはどんどん言っていきました。そういう方が楽しいですし。
德岡:ビジュアルや言葉のなんとなくのイメージまでは3人で話しながら共有し、その後は一気に、各自で磨いていきました。コピーは2人体制だったので、どちらかが何かしらを書いてきては、正しく意図が伝わるかという視点で議論していきました。忌憚のない意見を言い合える関係性だったのはありがたかったですね。大利からも、デザイナー的な視点からフラットに意見を言ってもらいました。

大利:1枚絵にするということは、必然的に一目で伝わるものにしなければならないということでもあったので、とにかくわかりやすいものにするということを意識しました。今回の僕たちの提案では、最終的に家庭で壁に貼って楽しんでもらいたかったので、インテリアとしても嫌じゃないものを目指しました。説明的であったり、広告臭がしすぎると嫌がる人が多いだろうなと思い。
チーム構成の話だと、3人でチームを組んだことが正解でした。2人だと意見がぶつかり合ったり、議論が煮詰まってしまうこともあるでしょうが、3人チームだと不思議とぶつかることもなく、どんどん意見を回していき、高め合っていくことができました。
德岡:今回、2023年の1月から3月までの間、隔週末はリアルで一緒に過ごしてきました。会えば5時間くらいは話していましたが、3人ともその濃密な時間に1ミリもストレスを感じなかったのが、一番の勝因だったのではないかとすら思っています。
大利:最初からたくさん出そうと決めていたわけではないけど、会うたびにアイデアが出てきて、結果的に点数が増えていき、今回の受賞にもつなげることができました。3人の相性がここまで良かったのは本当にラッキーでしたね。
松村:2人のおっしゃる通りです。

さりげなく社会を変えていけるようなクリエイティブを目指したい
―今回の制作を通じて気が付いたこと、またクリエイティブの力をどのように社会課題や問題解決に活かせると思いますか。
大利:僕は美大の卒業制作で、出身地である広島と原爆、戦争というテーマに取り組みました。その時も感じたのですが、結局、平和を守ろうとか隣人を愛そうとか言っても、テーマが大きすぎて手に余ってしまうんです。なので、被爆3世である僕自身にはどう見えているのか、という視点で取り組みました。大きな課題になればなるほど、当事者目線に立ち戻ることが大事だと思うし、それが唯一の方法なのかなと思います。今回も、僕らが子どもだった頃のことを思い出すことが、最初の一歩になりました。

德岡:世の中に顕在化している課題はいくらでもあって、クリエイターとしては、どれを選んで解決したいか?によって生き方が問われている時代。解決を目指すとしても、当事者意識が持てないまま走るのは危険だと思っています。今回の「ペラペラほんだな」に関して言えば、3人の共通認識として「小さい頃、こういうものがあったら嬉しかったよね」という想いがあって、当事者になれた。実は僕が子どもの頃は、本は嫌々読まされた記憶しかなくて、自分から読みたいと思ったことは、ほとんどなかったんです。「ペラペラほんだな」があれば、これ何だろう、と少なくとも興味を掻き立てられただろうとは思います。
松村:いわゆる社会課題だと言われてる環境問題やフードロス問題も、子どもが本に興味を持つきっかけをつくるという課題も、誰かが生きやすくなったり誰かの人生が豊かになるという点では、本質的には同じなんじゃないかと思います。
德岡:テーマが大きいと、ターゲットがぼやけてしまいますよね。特定の誰か一人を想定し、その人の悩みを解決できるだろうかと考えた方が、リアリティのある答えが出せる気がします。
―今回の体験を、これからの業務にどのように活かしていきたいですか。
大利:普段の仕事でも、MZ世代をターゲットに…とか、新しい市場開発を…など様々なオリエンが来ますが、それも一つひとつ当事者として考えることが一番の近道になると思います。自分の中にある答えを見つけた方が楽だし、それしかないんじゃないかなと思っています。
松村:これからデジタル化がどんどん進み、広告の形もどんどん変わっていくと思います。でも「そこに心を動かす何かがあるか」というのは昔もこれからも1番大事な要素な気がしています。それを忘れずに働いていきたいです。
德岡:クリエイターとしては、社会課題解決系のアイデアを、いかにも、と思わせないアイデアにできるかが問われている気がします。見た人に意識させることなく、知らず知らずのうちにさりげなく社会課題を解決できているようなクリエイティブがつくれたら。「気づいたら社会が変わっていたね」というアイデアを目指していけたらと思います。
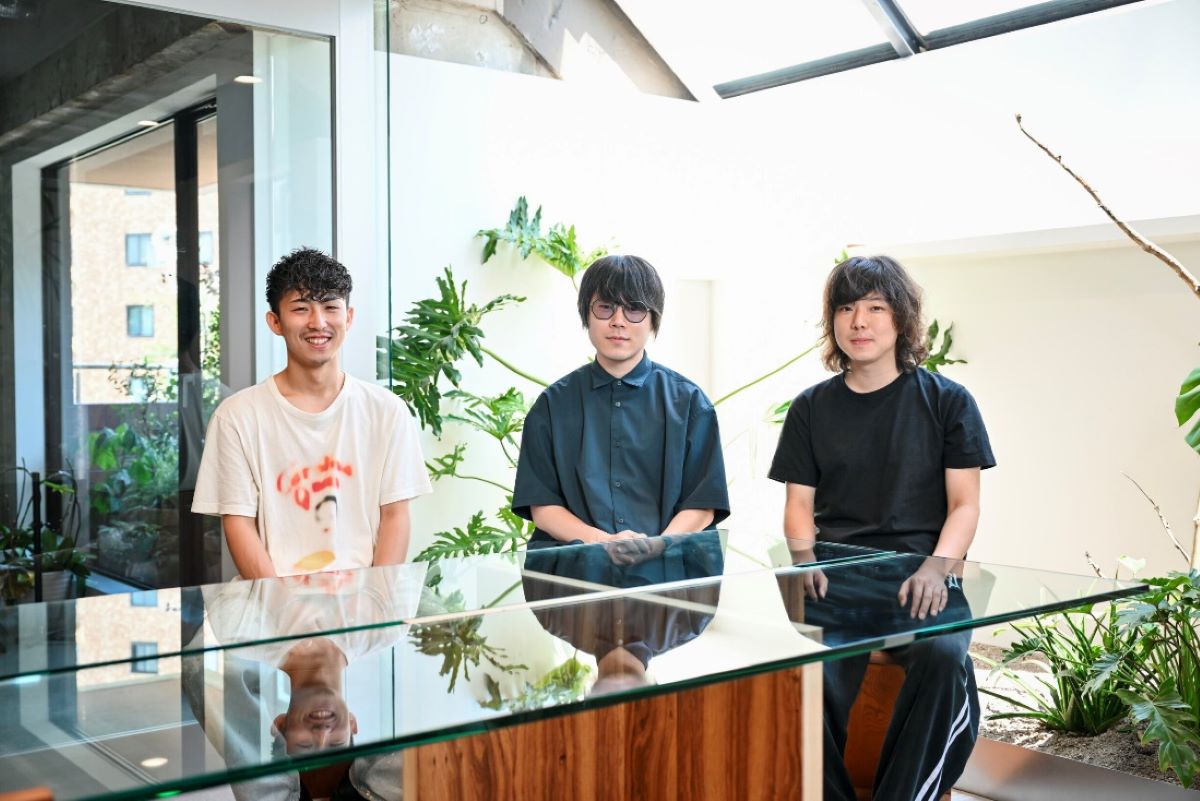

hakuhodon DXD 【デザイナー】
1998年、広島生まれ。2020年、武蔵美卒業、同年博報堂入社、H/designに配属。
2023年、hakuhodo DXDへ。
主な受賞歴に、朝日広告賞グランプリ、準グランプリ、入選など

博報堂 αクリエイティブ局 【コピーライター】
1996年、大阪生まれ。2020年、博報堂入社。TBWA\HAKUHODOを経て、現部門へ。
主な受賞歴に、TCC新人賞、OCC新人賞、朝日広告賞 グランプリ、ヤングカンヌ FILM部門 日本代表など。

博報堂 ブランドトランスフォーメーションクリエイティブ局 【コピーライター】
1997年、新潟生まれ。2020年、博報堂入社。
主な受賞歴に、BOVAグランプリ、朝日広告賞グランプリ、毎日広告デザイン賞準グランプリ、ACC賞など。








