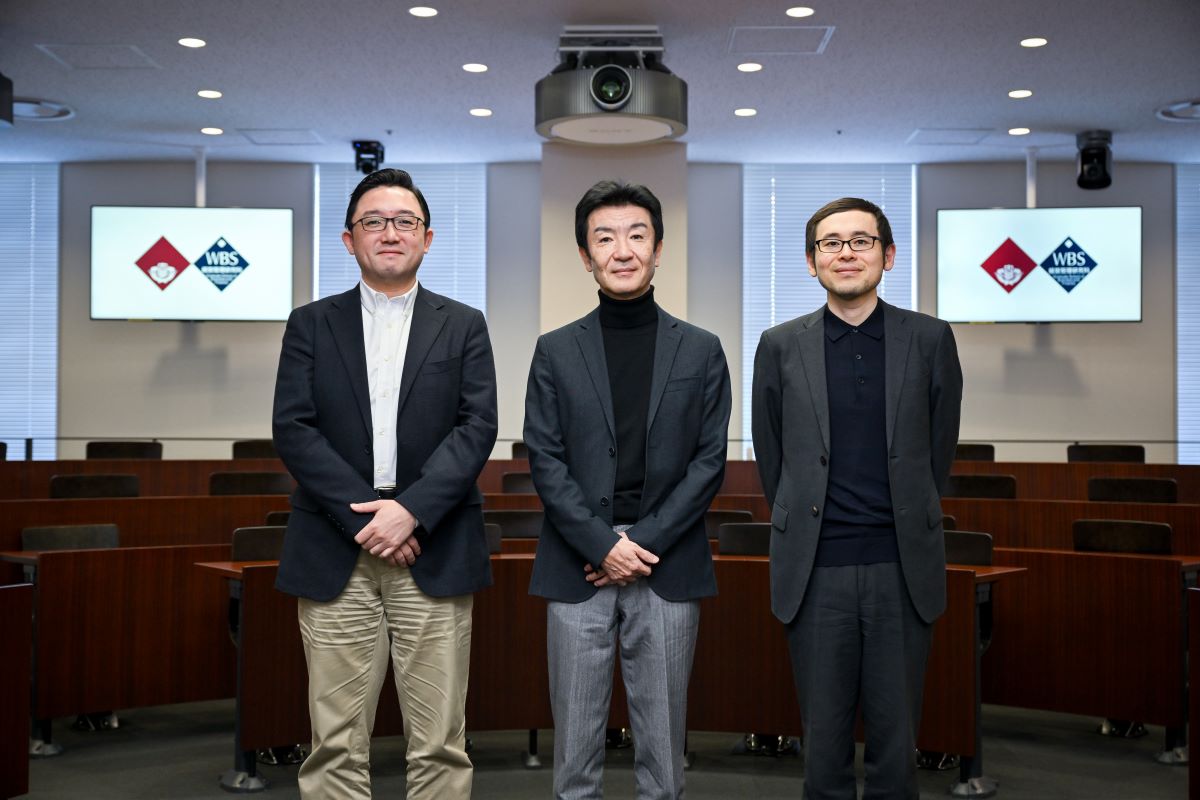
インターネットやスマートフォンが社会を変革したように、生成AIも過去に匹敵するパラダイムシフトを起こし 、広告やマーケティングにも大きな影響を与えると言われています。生成AIはビジネスをどのように変革し、新たな社会を切り拓いていくのか。
博報堂DYホールディングスは生成AIがもたらす変化の見立てを、「AI の変化」、「産業・経済の変化」、「人間・社会の変化」 の3つのテーマに分類。各専門分野に精通した有識者との対談を通して、生成AIの可能性や未来を探求していく連載企画をお送りします。
第9回はデジタル環境下の消費者行動論を研究されている早稲田大学大学院経営管理研究科 教授の澁谷 覚氏に、「AIとマーケティング」をテーマに生成AIが消費者行動やコミュニケーションに及ぼす影響などについて、生成AIも含めた先進技術普及における社会的枠組みの整備・事業活用に多くの知見を持つクロサカ タツヤ氏とともに、博報堂DYホールディングスの西村が話を伺いました。
澁谷 覚氏
早稲田大学大学院経営管理研究科 教授
クロサカ タツヤ氏
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任准教授
株式会社 企(くわだて) 代表取締役
西村 啓太
博報堂DYホールディングス
マーケティング・テクノロジー・センター 室長代理
株式会社Data EX Platform 取締役COO
生成AIは「ソーシャルグラフ」になれるのか
西村
人間・社会の暮らしに大きな変化をもたらす生成AIについて、まずは澁谷先生のお考えをお聞かせください。
澁谷
2023年は生成AIがブレイクした年だとすると、2024年は「GPTs 」の登場を機に生成AIを活用したサービスが決定的に浸透して、使う人と使わない人の差が出てくる年になると予測しています。私自身もいちユーザーとして、2023年には当時のプラグインストアからいくつかのプラグイン(拡張機能)をインストールして利用していましたが、生成AIのプラグインは非常に豊富で、使い方次第で生産性を大きく向上させると感じていました。今年はいよいよGPTsの利用が広がり、生成AIが“あなたにとってどう役立つか”という非常に具体的な形として台頭するのではないでしょうか。
西村
昨今では、検索エンジンにも生成AIが組み込まれてきたことで情報の取得行動自体も変わってくるのではと感じています。先生はこれまでのデジタル環境下の消費者行動研究において、個人間のコミュニケーションを「オンライン/オフライン」および「ソーシャルグラフ/インタレストグラフ」という2つの軸で分類されていますが、生成AIによって人々の情報取得行動が変わるなか、「ソーシャルグラフ」と「インタレストグラフ」の関係性や人々の行動はどう変わっていくのでしょうか。
澁谷
「ソーシャルグラフ」は当事者間の社会的関係を、「インタレストグラフ」は興味・関心が近い当事者間を結びつける関係を指します。インタレストグラフの方は「面識がない人同士の興味・関心の一致性」なので、インターネットやSNSを検索して自分の興味があることを調べて、誰かが紹介してくれている知識・情報を通じて発生するつながりが代表的かと思います。知りたいことを生成AIとの対話を通じて調べるという新しい生活者行動が発生した場合、インタレストグラフは生成AIに模倣されるかもしれません。一方で、インタレストグラフからソーシャルグラフへの移行、例えば、“ビジネススクールの入学式で知り合った人“という、当初は”MBAに関心がある“という人同士のインタレストグラフが、実際にスクールに通うなかでソーシャルグラフの知り合いに移行していき、人同士の関係性が育まれていく。こういった体験を生成AIでできるかどうかはひとつのテーマになってくるでしょう。また、教科書で学ぶ時代から動画で学ぶ時代へと変わってきた直近10年を経て、これからは“AIで学ぶ時代”になるといわれています。つまり、生成AIが一番優れた先生で、生成AIと共に育った人たちが社会に出てくるときに、そういった「AIネイティブ世代」にとって生成AIが単なる情報・知識の提供相手を超えて、ソーシャルグラフのつながりを感じるようになるか否かというのは、非常に大きな研究テーマだと捉えていますね。

そこで肝になるのが、“生成AIに何か頼むと返ってくる”という依頼ベースの関係ではなく、生成AIがエージェントになって我々の気持ちを汲み取り、“生成AIの方から提案してくる”ように進化できるかどうかということです。人間は生成AIと友達になれるか、という研究をいくつか見てきましたが、結論として会話中に生成AI側から働きかけることがないと、なかなかお互い親密にはなれないようです。会話の中で相互の貢献を認め合い、その上に話をのせていくような人間同士のコミュニケーションが生成AIにもできるのか。現段階では生成AI側から新たな文脈の提案が来ることはないので、“人間とAIが親密になる”という世界は、もう一段の進化の先にあると思いますね。








