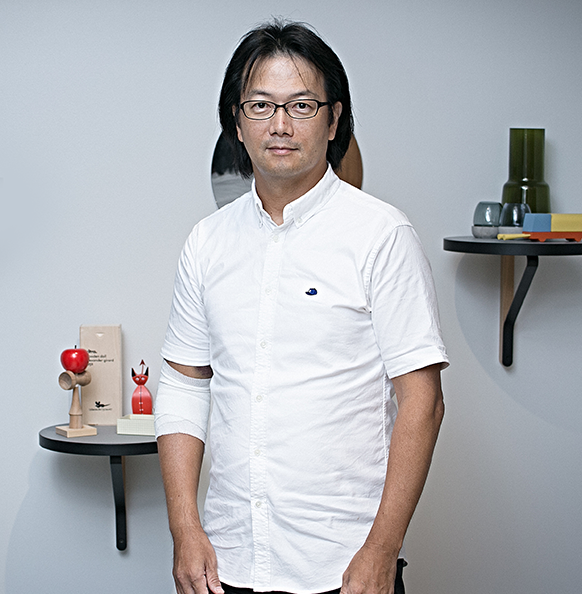マーケティングとは、本来、イノベーションである!
土屋 私は、様々なクライアントとお仕事をさせて頂いておりますが、デジタル化の流れもあり、マーケティングがますますオペレーティブになってきていると感じています。イノベーションが注目されている一方で、マーケティングが定型的な作業になってしまっていることを懸念しています。
楠木 マーケティングというものが、定型的でつまらなくなっているということでしょうか。私の考えでは、進歩は物事をつまらなくするってことなんですよ。マーケティングという概念や機能に関する知見が積み重なり、さまざまな方法や手法が開発されてきた。つまり、マーケティングがスキル化すると、労働市場が形成され、そこで非常に効率的な人的資源の配分が行われる。更に、人的資源の成長が促されると、専門的なスキルで測られていく。これは、ある進歩が設定された上に、より良くなっていくという、エンジニアリング的なことになってしまっているということです。
土屋 そもそもマーケティングやイノベーションをどのようなものだとお考えですか?
楠木 イノベーションに関して一般に共有されている理解は、根本的に間違っていると思うんです。改めてその定義をはっきりさせると、製品やサービスの「進歩」ではないということなんです。「進歩」という概念は、昔からあって、たかだか100年ぐらい前に、「進歩」ではどうしても捉えられない現象を捉えるために、「イノベーション」という新しい概念が必要になったわけです。50年以上前のドラッガーの定義によれば、価値次元の非連続性ですね。要するにパフォーマンスの次元が変わるということがイノベーションだといえます。
土屋 イノベーションとは、製品やサービスのパフォーマンスそのものや、性能が良くなるということではなく、生活者が受け取る価値の次元が変わるということなのですね。
楠木 今は、イノベーションのそもそもの意味合いが忘れられてしまって、斬新なものが出てきたとか、すごく進歩した、ということがイノベーションの意味合いになってしまって変なんです。例えば、1日5分充電すれば、1年間充電が必要ないスマートフォンはイノベーションではないわけです。
土屋 そうした技術的に優れた商品でも、一般的にはイノベーションって言われていますね。
楠木 それは、単なる「すごい進歩」なんです。ある価値の次元なり、パフォーマンスの次元がセットされ、それをみんなが受け入れて、どれだけ先に行けるのかっていうベクトルの大きさを争うのはスキルであって、エンジニアリングです。
土屋 一方で、生活者に対して新しい価値を提供し、市場で価値を交換することがマーケティングだとすれば、「マーケティングとは、本来、イノベーションである」ということだと思います。本来的には、新しい価値次元をつくることを含めて、マーケティングであるにもかかわらず、実際の現場では、マーケティングが効率ばかりを求めすぎているということに問題があり、マーケティング本来の姿を実現していないんじゃないかと考えられます。

イノベーションは人間の本性に反している
楠木 イノベーションは、供給よりも需要に深く関わっているものだといえます。ハイブリッドエンジンの進化は、燃費がよくなって、良いことだけど進歩にすぎません。対して、お客さんが求めている、これまで自動車になかった価値の次元を発見して、従来の価値次元からシフトしていくというのがイノベーション、かつ、マーケティングなわけです。今のマーケティングは、本来のものから少し外れてしまっています。
土屋 なぜ、そういう風になってしまったのでしょうか?
楠木 人間は自分が一番大切なんです。仕事をする上でも、自分にとってインセンティブが利くもの、より高く評価されるということが大切なので、スキル化に向かうのは自然だと思います。
土屋 マーケティングの組織構造や社員に対するインセンティブの設計に原因があるということは、企業を経営する側の問題が大きいということでしょうか?
楠木 人間の本性に合わせて制度が作られているわけです。つまり、イノベーションっていうのは人間の本性に反する面があるので、出来事としては非常に稀なわけです。
土屋 マーケティングに携わっている立場からすると、今ある製品やサービスの効率、性能を高め、世の中に普及させていく方向にインセンティブを強く感じはするものの、価値次元を変える、新しいリスクを伴うようなことは、なかなか行動に起こしづらいというのが実際だと思います。
楠木 例えば、進歩であれば、「社長、この技術に投資しましょう」、もしくは、「このマーケティングの活動に投資しましょう」と提案すると、リソースを出す側は、「どんないいことがあるんだ?」となる。進歩であれば価値の次元は変わらないので、「この技術に投入していただければ、今までよりも半分の消費電力になるチャンスがあります」とか、「このマーケティング活動に投資すれば、われわれの製品を知っている消費者が3倍になる見込みがあります」と。そうすると、社長は「そうか」となって決済する。進歩は、組織的な正当性が獲得しやすいわけです。ところが、「何が良いか」という価値次元自体が変われば、「お前、遊んでないで仕事しろ」という話になってしまいます。
土屋 価値次元の異なるイノベーションは、事前に結果を測定しにくく、そもそもそのインパクトがイメージしにくいものですからね。
楠木 むしろ今までの価値次元からすると、何かを大きく失うわけです。それは、普通の人にとって嫌なことです。
土屋 多くの企業の経営者が、「今、一番必要なことはイノベーションだ」と言いながら、社員に対して、イノベーションに対するリターンを事前にきちんと求めるという姿勢に矛盾があるのでしょうか?
楠木 単に定義の問題で、経営者が「イノベーションが必要だ」と言った時、「どんなものを言ってらっしゃいますか?」と聞いてみれば、その真意は、「進歩」にあることがほとんどだと思います。
土屋 「性能を上げろ」とか。「もっと売れるようにしろ」とかという、同一の価値次元上での「進歩」ですね。やっていることは変わらない。方向性も変わらない。すなわち、「イノベーション」ではないということですね。
楠木 現代において、経営者自らがイノベーションを起こすということは極めて難しいと思います。特に上場企業の場合、ステークホルダーたちは、最もイノベーションを嫌う人たちですから。口では「イノベーションをやれ」と言っていても、彼らが気にしているのは四半期の棒グラフだけです。これはまさに進歩的なベクトルです。そういう株主のプレッシャーを受けながら、価値次元を変えるというのは、経営者にとって極めて難しい時代だと思います。
「何が良いか」が変わるというのは、究極のWhatであるべきです。本来のマーケティングがイノベーションを創出することから外れてしまいがちになっていますが、しかたがないのかもしれません。世の中の進歩の一側面かもしれません。
土屋 Whatを考えるということで言えば、過去10年から20年の間、マーケターは、ブランドというものをすごく大事にし、ブランディングに取り組んできたと思うのですが、私は最近、ブランディングそのものがイノベーションの足かせになっていると思う時があります。「変わらなければ、同じ場所にすらいられない」という言葉がありますが、本来、ブランドは、時代にあわせて変化するものであるにもかかわらず、価値を規定し、形を創って、研ぎ澄ませば、研ぎ澄ますほど、これまでの価値次元から抜けられなくなるというような状況に陥ってしまっていると感じています。
楠木 企業のマーケティング部門が既存の価値次元に縛られているとしたら、それは組織のことをよく知ってるんだけれども、その会社の中にはいない人、つまり、博報堂のような立場の人の意味というのが大きいと思います。
土屋 外から見て、もしくは、生活者の側から見て、「このブランドの価値次元はこう変えられるんじゃないか」とか、「このリソースはこう使えるんじゃないか」とか、そういう発想が求められるということですね。
楠木 そうです。だからリソースは企業の中にあるんですが、そのリソースをどう使うかという問題は、中の人間は既存の価値次元に縛られているので、外部の人の方が提案しやすいということです。オープンイノベーションの概念はリソースの話だと思うんです。あるベンチャー企業がAというリソースを持っていて、大企業がBというリソースを持っている。ある案件を成し遂げるためには、AとBの両方のリソースが必要なので、効率的にオープンイノベーションをする。
土屋 これまで議論してきた通り、イノベーションが製品やサービスのパフォーマンスの改善ではなく、価値次元の変化であるとするならば、イノベーションは、例えば、技術といった企業が所有するリソースの進化に依存しないということだと思います。生活者が潜在的に求めているという前提の中で、「良いもの」の定義を発見できれば、製品やサービスの性能は必ずしも進化しなくてもよい。それでも、イノベーションを起こせるっていう発想に立つからこそ、価値次元が違うものになると私は考えています。
楠木 そうです。シュンペーターが新結合という表現をしたのは、実は本当に言いたいことは非連続性なんです。有名な比喩で、どんなに馬車を連ねても、それは蒸気機関車にならない。要するに非連続性を言いたくて、その非連続性の表現として新結合と言ってるんです。イノベーションって、私は路線転換だと思うんです。「何が良いか」が変わること。路線転換者がイノベーターである。スティーブ・ジョブズさんもそうだったんだと思うんですけど。それはかなり自由で、ステークホルダーからの利害からも解放されている。
なんでそんなバカなことをやるんだって思うような、 良いことがイノベーションにつながる
土屋 マーケティングをどうクリエイティブにするのか、イノベーションに繋がるコンセプトをどうつくれるかっていうところの大きなポイントは、競合からすると真っ当だと思われている、もしくは、競合がこれ以上身動き取れないなって思っている方向性とは異なる方向性で、しかも、生活者が望むコンセプトを作るということなのではないかと思っています。

楠木 おっしゃる通りですね!だから、ちょっと邪道と言えば、邪道なんですが、まず業界で今、とにかくみんながほぼ無条件でいいと思っていることをリストアップしてみる。その上で、その逆を考えてみるというのが良いと思います。
土屋 「良い」ということの意味を変えるのがイノベーションだから、良いものをリストアップした上で、競合がやらなそうな、新しい「良い」ものを見つけるということですね。
楠木 しかも、その良いものリストは、ほぼ全員が無条件で絶対にいいと思っていることがいいですね。進歩の余地がある時は、何ら問題ないんです。イノベーションなんて大きなお世話だと思うんです。ところが、成熟してくると、進歩には終わりがあります。
土屋 それは、オーバーシューティングということですよね。製品やサービスのパフォーマンスが進化しても、生活者が求める水準を超え、生活者がその進化を知覚できなくなってしまっては意味がありません。
楠木 そう。物理的、機能的により良くできても、お客さんが吸収できないですよね。ですから、そうなると何が良いかを変えなきゃいけないので、文字通りイノベーションが大切になる。そういうときにはみんながいいと思っていることをさらに良くするっていうのは意味がない。そのためには、むしろ、今、みんなが絶対にやっちゃいけないと思っていることを考えてみるっていうのはおおいにありですね。
土屋 「そんなバカなこと、なんでやるんだ」って思うような、「良い」ことです。相手を出し抜くというような競争の視点で考えると、ちょっと邪(よこしま)に聞こえてしまうかもしれないですが、生活者とか、世の中から求められている価値であれば、すごく純粋な動機に基づいた新しいコンセプトになる気がします。
楠木 おっしゃる通りですね。難しいのは、人間の本質的なニーズは、必ずベールがかかっているという感じなんです。つまり、イノベーションっていうのは出てきちゃうと、みんなが「なんで、こんなの無かったのかな?」と思う。極めて常識的なこと。要するにニーズを正面から捉えているんですが、そのニーズ自体が覆い隠されていると。
土屋 そのベールに包まれている潜在的なニーズをはがすようなことが必要だと思います。
楠木 つまりこういうことですね。友達の本質は非経済性なんです。ところが、仕事で知り合った人って、プライベートで仲よくなったとしても、非経済性がないんですよ。仕事で仲よくなったけど、それぞれの立場とか利害があって。常識に反するっていうことは、非経済性より、反経済っていうか、企業の中にいる人にとっては、利害がある人から話を聞くと駄目だと思うんですよ。だから、業務とは関係ないところから入ってくる声みたいなのが、実は大きな意味があるんですね。
土屋 我々がクライアントとの関係性を考える上で、とても参考になる視点です。「友達」とはいかないかもしれませんが、「反経済」というか、利害関係を超えたところで、共通の目的をもって接したいと真摯に思います。本日は、どうもありがとうございました。
対談を終えて(土屋 亮)
「バカな」と「なるほど」を、誠実に。
マーケティングは、本来、イノベーションであるにもかかわらず、効率化を求めるあまり、オペレーティブになっている点を懸念していましたが、楠木教授とイノベーションの本来的な意味を議論することで、マーケティングをクリエイティブにするための活路を見いだせたように思います。
イノベーションは、面白い思いつきでも、製品やサービスの性能向上でもありません。これまでとは「良い」の基準を変えることであり、一見すると「バカな」と思われるが、ひとたび市場に出れば、正面からニーズをとらえた「なるほど」が感じられる事象です。そう、イノベーションは、需要側の論理なのです。
こうした既存の価値次元からの解放はリスクを伴い、かつ、企業内部からの発想が難しいという議論は、「生活者発想」を理念として掲げる博報堂の存在意義を感じさせてくれました。同時に、我々は、生活者や社会に対して、誠実でなくてはいけないという点で、身が引き締まる思いをいたしました。
マーケティングには、社会や組織を大きく変える力が備わっています。ただ、その力を引き出すためには、私利私欲を超えて、社会や生活を見つめ、既存の価値次元からの解放に果敢に挑戦しなければなりません。本対談を通じて、こうした「志」をともにできるクライアントの皆様と、「良い」社会づくりに取り組んでいきたいと改めて思いました。
Profile
楠木 建
幼少期を南アフリカ共和国のヨハネスブルグで過ごし帰国。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了後、イノベーション研究センター助教授を経て現職に。専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位性を維持する研究を行なっている。2011年、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』でビジネス書大賞を受賞。本格的経営書として20万部を超えるベストセラーを記録し、実務家にも大きな影響を与えた。プライベートではBluedogsというロックバンドでベースを担当し、精力的にライブ活動も行なっている。自分の仕事についても「本はアルバム、論文はシングル、講義や講演はライブ、経営助言はジャムセッション」と、音楽のメタファーでとらえている。近著では『「好き嫌い」と才能』(東洋経済新報社)、『好きなようにしてください:たった一つの「仕事」の原則』(ダイヤモンド社)など、著書・論文を多数発表している。
土屋 亮
営業局、経営企画局を経て、ペンシルバニア大学ウォートンスクール卒業(経営学修士)。現在は、飲料、食品、トイレタリーなどを担当し、事業戦略、新規事業開発やサービス・デザイン、マーケティングプラニングに従事。