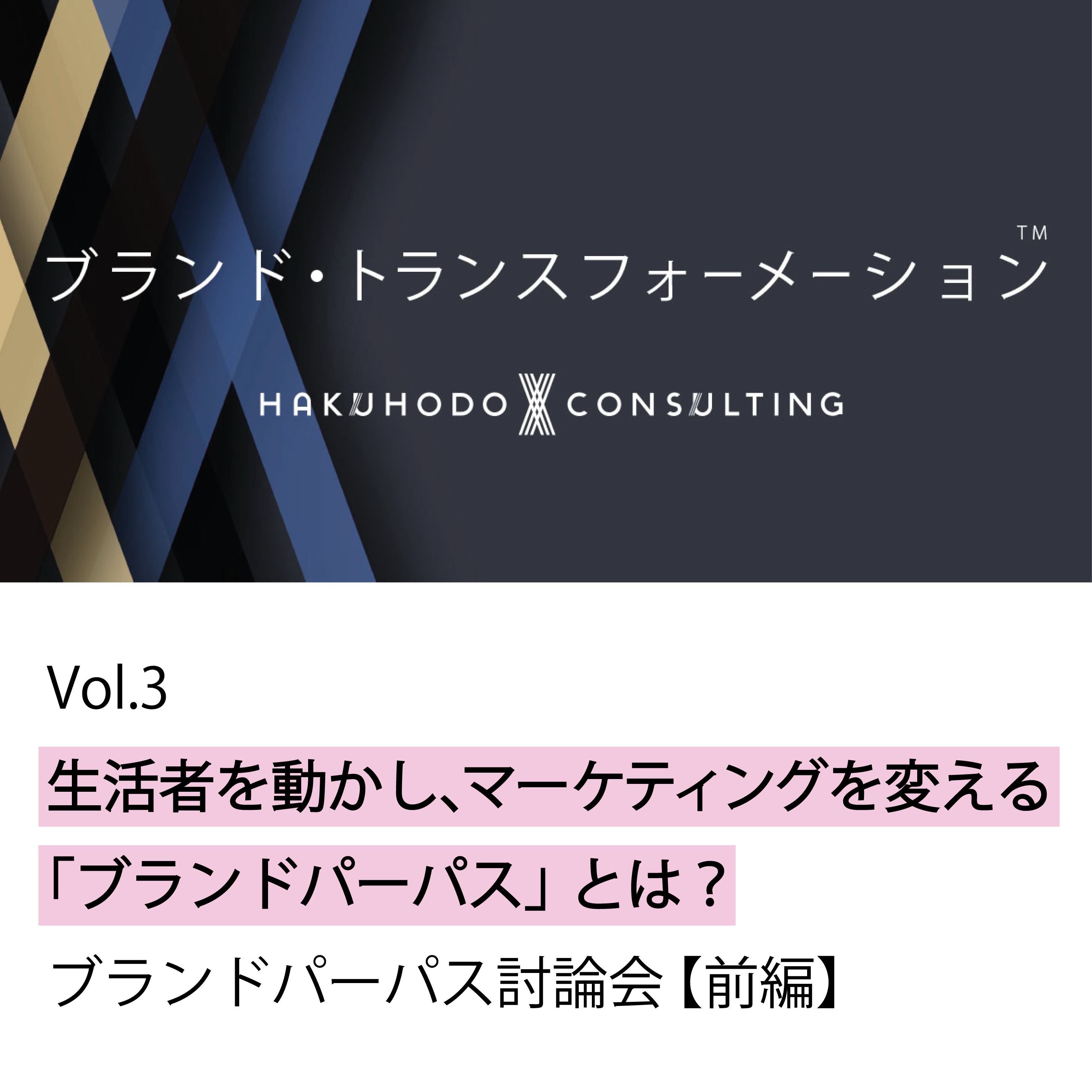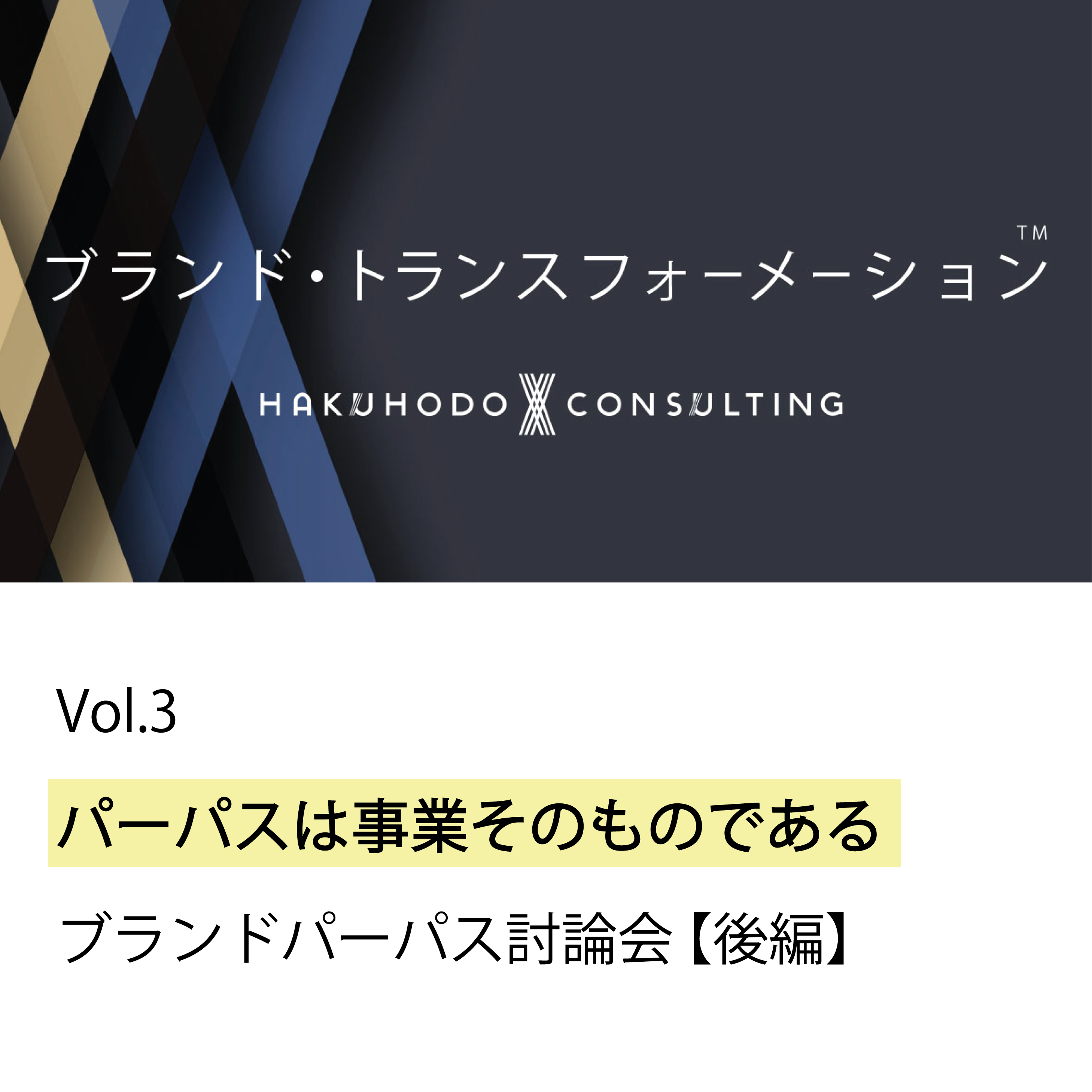「ブランド発想」がDXを成功に導く──ブランド・トランスフォーメーションによる企業・事業変革の新潮流
(HAKUHODO X CONSULTINGセミナーレポート)

スピーカー:宮澤 正憲
(HAKUHODO X CONSULTING推進リーダー/博報堂ブランド・イノベーションデザイン代表)
「プラスを創出する」DXとは
宮澤
日本の国際競争力の衰退が止まりません。IMD発表の2020年のランキングでは、過去最低となる34位にまで後退しています。特にこの要因となっているのが、生産性や効率性、経営の意思決定スピードといった「ビジネス効率性」の低下です。こうした背景もあって、最近の経営の大きなイシューであるDX(デジタル・トランスフォーメーション)では、いかにオペレーションを最適化して無駄を削減し、生産性・効率性を向上させるか、という観点に目が行きがちです。
しかし本来、DXには効率性の向上だけではなく、もう一つの重要な側面――事業転換や事業開発によって「新たなプラスを創出する」という目的があります(図1)。多くの企業が現状では効率化のDXにとどまり、顧客体験の改革や、ビジネスモデルを抜本的に改革するような価値創出型のDXに取り組めている企業は、まだ多くありません。ですが今後は、いかにプラスの付加価値を上げていけるかがDXの主戦場になっていくことは間違いないでしょう。

当然ながら、そうしたDXの実現は容易ではありません。上手くいかなかったケースを探ってみると、そもそもDXに取り組む「目的」がよく分かっていなかった、という話がよくあります。DX自体が目的化して、「何のためにやってるんだっけ?」となってしまう。DXはあくまで手段だということを忘れてはいけません。
そのほかにも、旧態依然とした組織文化に阻まれて変革が進まない、推進する人材がいない、限定的な改善で終わって継続しない、競合他社と似たシステムを取り入れた結果、他社と同質化してしまったなどの問題も起こっています。
DX成功のポイントは、まさにこういった問題点の裏返しと言えます。トランスフォーメーションした先に何があるのかという目的を明確に見据えた上で、手段としてのテクノロジーやデータを活用しながら、事業そのものや組織の変革によって「その企業ならでは」のDXを推進していくことが肝要です。
「その企業ならでは」とは、独自性や自社らしさ、つまり「ブランド」です。実はDXの推進において、ブランド的な考え方、ブランド発想を入れ込んでいくことが、他社にはできない独創的な変革を実現するカギとなるのです。
「ブランド」の概念が変化している
宮澤
昨今、経営において「ブランド」が再注目されています。私自身長くブランドコンサルティングを専門にしていますが、昨年からはコロナ禍もあり、自社のブランドをもう一度つくり直したいという経営層からのご相談が非常に増えています。
現在、国内外で「成功している」と言われているブランドを見てみると、一昔前までのブランドとはかなり性質を異にしていることがわかります。かつてのブランドはモノが中心で、機能価値や情緒価値を軸に、広告やさまざまなタッチポイントを駆使して良好なイメージを形成するブランディングが行われていました。ところが今、ブランドの中心はモノではなく「サービス、事業そのもの」へと移行しています。無形のサービスはビジネスモデルそのものと直結している場合も多く、もはや企業活動、事業活動自体がブランドの核になってきています。
さらに、ブランディングのプロセスにも大きな変化が生じています。それは「共創」がブランドのつくり方の前提になっていること。従来のブランドは企業がつくり、一方的に生活者に提供するものでしたが、今のブランドは社会や生活者と一緒につくるもの、生活者が「参加するもの」へと変化しているのです。
生活者の購買シーンの変化をイメージすると、分かりやすいと思います。ブランドは今まで、「どこで買おうか、どれを買おうか」と悩んだ際の選択・判断のサポートとして機能していました。ところがサブスクやメンバーシップ型などの新しいサービス形態が次々と生まれ、アプリでつながっている企業にメッセージを送るだけで手軽に注文できる状況においては、何を買うかは実際の購入時ではなく、それよりもずっと前――最初にこのサービスのメンバーになろう、このブランドに参加しようと思った段階で既に決まっているわけです。
そうなるとブランディングの力点も大きく変わります。企業は、どうやったら買ってもらえるかという発想から、「どうやったら参加してもらえるか」という発想に切り替えなければならない。特に核になるのは、参加してもらうためのサービスや事業そのものをどうつくっていくかです。これからの企業変革・事業変革において、この観点は不可欠と言えます。

ブランド・トランスフォーメーション推進の4要素
宮澤
我々博報堂は、こうした次世代型のブランドの考え方を取り入れた事業変革を「ブランド・トランスフォーメーション」と名付け、企業向けのコンサルティングサービスを行っています。その中身を少し紐解いてご説明したいと思います。
トランスフォーメーション、変革と一口に言っても、実際はさまざまな変革を複合的に行わなくてはなりません。どこか一つだけ変えようとしても、往々にして何かが上手くいかなくなります。ある目的を達成するために必要な変革ポイントを見定め、それらをどう連関させていくかという視点が重要です。我々が企業のブランド・トランスフォーメーションを検討する際、特に重視するのは「パーパス」「事業・組織」「生活者体験」「コミュニティ」という4つの要素の変革です。(図3)

【パーパスの変革】~企業の存在目的が問われる時代~
今非常に注目されているパーパス。一人称で発していた理念やビジョンとは違い、社会的にみた自社の存在意義を表明するものです。いまや企業レベル、事業レベル、ブランドレベル――あらゆるレベルで「社会的な存在意義」が問われる時代になっています。
背景には世界的なサステナビリティ重視の流れもありますが、ブランディングやマーケティング的に最も大きいのは、「共感」がブランド選択の基準になってきている、という事実です。商品の機能の良さや値段ではなく、企業やブランドの姿勢に共感したから買うという人がとても増えている。特にミレニアル世代ではその傾向が強くみられます。こうなると、お客さんに共感されるパーパスを掲げることが非常に重要になってきます。
一方、パーパスを掲げただけで終わってしまうことは危険で、逆効果になる可能性もあります。パーパスに紐づいた具体的な商品や具体的な事業を提供することは不可欠で、「こういうパーパスを達成したいから、こういう事業変革をします、こういう商品をします」というところまでがつながって、はじめてパーパスの血が通い、お客さんもなるほどと理解してくれるわけです。
パーパスを新たに設定したり、変えたりする際には、単なるお題目にならないよう、そこに必ず事業や組織のトランスフォーメーションを呼応させていくことが重要です。
【事業・組織の変革】~事業変革とマッチした組織変革の必要性~
組織論の大家であるヘールト・ホフステード教授は、「組織文化に良いも悪いもなく、戦略やゴールに合ってるかどうかが大事。合っていれば効果を生むが、合わないと逆に阻害要因になる」と言っています。戦略とゴールはここでいうパーパスですが、事実、パーパスの内容と実態にずれがある企業は、かなり多くみられます。ずれているだけならまだよいですが、教授が指摘するような「阻害要因」になるリスクを考えると、時間はかかっても、目指す事業変革とマッチした組織文化の変革に手を付けることも一つのポイントになるでしょう。
とはいえ日本の大企業で、組織文化をがらりと変え、大きく事業転換することはとてもハードルが高いことです。現実的に進めやすいのは、出島をつくるなどして、小さな事業や商品から別ブランドを立ち上げ、そこから大きくしていくやり方でしょう。代表的な手法がいま非常に伸びているD2C(Direct to Consumers)で、当社でもコロナ以降、D2C立ち上げのご相談を多数お受けしています。海外ではかなり大規模なビジネスに成長しているD2Cもありますが、日本の場合は、D2C自体で儲けようとするのではなく、新たな変革のきっかけとして試金石的に行ってみて、上手くいけば事業として拡大し、ビジネスの核にしていく形がよいのではないかと思います。
【生活者体験の変革】~統合された新しい体験が生まれる~
成功しているD2Cブランドに共通しているのは、生活者に「他にない体験を提供できている」という点です。ビジネスモデルの変革を考える上では、顧客体験、生活者体験をいかにトランスフォーメーションしていくかも密接に関係してきます。
いま、バリューチェーンの構造が大きく変化しています。全体がデジタルとデータによって統合され、生活者を中心とした新たな体験の構造が生まれています(図4)。博報堂ではこの新たな世界を「生活者インターフェース市場」と捉え、ブランドと消費者の接点が双方向化し、インターフェース化されていくことによって、今までになかった新しいサービスや体験が次々と生まれていくと考えています。

ここでのポイントは、生活者の側から見て、その体験がどう見えるかということです。ユーザーからすると、従来は個別に提供されていたサービスやアクションが、一つの統合されたサービスになっていくということ。健康管理を例にすると、これまではバラバラに行っていたフィットネスクラブに行く、シューズを買う、栄養補助グッズを買う、大会に参加するなどの行動が、スマホの中で一つの健康管理サービスとして統合されていきます。別の会社だろうと、異業種だろうと、生活者からみると一つの体験になるのです。
このこともまた、ブランドのつくり方に大きく影響します。これまで以上に他企業や異業種とのコラボレーションや共創が大事になっていきます。ブランド構築、生活者体験の構築においてもオープンイノベーションの重要性が高まっていくと考えられます。
【コミュニティの変革】~ブランドのファンとともに共創する~
先ほど述べたように、これからのブランドや事業は、ユーザーにいかに参加してもらえるかが非常に大きなポイントです。そのためにどのような「コミュニティ」をつくり、どうやって発展・維持させていくかを考えねばなりません。
コミュニティと聞くと、コアなファンの集まりを想像される方もいるかもしれませんが、ここでいうコミュニティはもう少し広く、そのブランドを応援している人や、ブランドが好きな仲間の集まりといった概念です。ただ、「顧客にかぎらない」ということが非常に重要で、買った人もいれば、買わない人もいる。でもみんなそのブランドを応援している。そうしたコミュニティをいかにマネジメントし、いかに「共創」につなげていけるかが、今後のビジネスの大きなポイントになると考えています。
コミュニティが上手く機能すると、参加者のLTV(ライフタイムバリュー、生涯顧客価値)を高めるだけでなく、他者への推薦や、新規の顧客を呼んできてくれる効果も期待できます。
しかし現状では、こうした企業のコミュニティ運営は、それほど上手くいっているとは言えません。既存顧客だけで閉じてしまいLTV向上の効果が小さいという問題や、参加者は必ずしもよい情報を発信してくれるわけではない、コアなファンの発言力が強すぎて新規顧客が入りにくいといった問題が起こっています。
こうした問題を改善するためにも、商品開発や事業開発などに参加してもらう共創活動とCRMを組み合わせて、参加者を増やしながら、LTVを向上させていくコミュニティをいち早く構築し、育成していくことが重要と考えられます。
WIREDの元編集長であるクリス・アンダーソン氏は、「今後、コミュニティ主導ビジネス以外は生き残れない」と明確に言っていますが、私もまったく同感です。
事業を回し続け、変革し続けていく
宮澤
以上、プラスを創出するDXの推進においては、ブランド発想が鍵を握っていること、そして「ブランド・トランスフォーメーション」を推進する4つの要素について、簡単にご説明しました。4つの要素の変革は、必ずしも図で示した順序で進めるとは限りませんし、すべてに取り組まねばならないという意味でもありません。しかしどれか1つの変革だけではなく、2つ、3つの変革を複合的に進めながら、事業を常に回し続け、変革し続けていくような動的なビジネス、動的なブランドづくりに取り組んでいくことが、社会にとって魅力的で独創的な企業活動の創造へと必ずつながっていくはずです。
博報堂は、ブランド・トランスフォーメーション推進のための専門性と知見をグループ横断で結集させ、最適なチーム編成でクライアント企業の支援に取り組んでいます。ぜひご相談いただけたらと思います。

HAKUHODO X CONSULTING推進リーダー
博報堂ブランド・イノベーションデザイン 代表
東京大学文学部心理学科卒業。株式会社博報堂に入社後、多様な業種の企画立案業務に従事。2001年に米国ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院(MBA)卒業後、ブランド及びイノベーションの企画・コンサルティングを行う次世代型専門組織「博報堂ブランド・イノベーションデザイン」を立ち上げ、経営戦略、新規事業開発、商品開発、空間開発、組織人材開発、地域活性、社会課題解決など多彩なビジネス領域において実務コンサルテーションを行っている。株式会社博報堂コンサルティング、及び 株式会社SEEDATA非常勤取締役。主な著書に『東大教養学部「考える力」の教室』『「応援したくなる企業」の時代』など多数。東京大学教養学部教養教育高度化機構 特任教授。
博報堂グループ横断で提供する統合コンサルティングサービス。「ブランド・トランスフォーメーション(BX)」を旗印に、次世代のブランド発想を基軸にしたアプローチで「ビジョン・パーパスを変革」し、「組織・事業・人を変革」し、「生活者体験を変革」することで、独創的な企業活動へ大胆にトランスフォームします。
>専用サイト https://www.hakuhodo.co.jp/hxc/